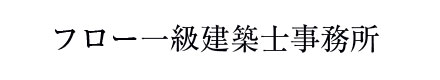知り合いに写真を見ながらなぜこうしたのかなどを説明をしていたのですが、それがおもろいと言ってもらえたので、ブログに載せたいなと思って、写真を見ながら説明をしたいと思います。
①障子を閉めたときに全体のトーンが下がることで障子の紙がキラキラと輝く(障子をあけると借景が際立つ)
明暗がはっきりしている方がより影が際立ち落ち着いた空間になる。
今回は障子紙に手漉き紙を使ったのでより柔らかい光が入ってくる。
壁を土壁にすることでより明暗がはっきりする。
②窓の上の土の壁
障子窓と天井との間にほんの小さな垂れ壁があります。
天井まで建具を伸せばこの小壁をなくすことができるのですが、なぜこんな小壁をつくったのか?
小壁を作ることで影ができより空間が包まれた感じになります。
あえて、小壁を作っています。
➂窓大きさ
腰かけたときに目線が心地良い高さにしています。
絞った窓にすることでより程よく景色が切り取れてより景色際立ちます。
借景をできるだけ取り入れるために幅は大きく、落ち着かせるために高さは絞るという感じです
➂壁
障子窓横の出隅の壁
窓を端から端まで設けるほうが解放感があるのでは?
あえて出隅の壁をつくる理由としては窓と壁をバランスよくつくる。
いい景色があるからといってすべてを窓にすると落ち着けるところがない。
置き照明の明かりを壁にあてることも目的のひとつです。
④畳の間の背もたれ
畳の間は当然座るところなのですが、一部に背もたれできる部分があるとよりくつろぐことができます。
背もたれの壁は写真ではわかりにくいですが、少し傾けています。
小上がりに少し触れておくと、小上がり畳は大きいソファーのイメージで作っています。
気軽に座れる高さであり、この柔らかい畳はお子さんが這いつくばるところだったり、洗濯物を畳んだり、ヨガをしたりで皆さんに重宝してもらっています。
⑤窓の下の腰掛け
窓の下に何を作るか?
以外に使い道はないのですが、収納付き腰掛にすることによって、居場所が増えます。
腰掛けることによって窓を眺める機会も増えます。
友人や知人が訪れた際はここに腰かけることは間違いないです。
⑥小さな簾戸
この窓のある方角はアプローチのあるきれいな庭でしかも隣地と距離がある程度あるため、セロリー的には庭を眺めるように大きな窓を設けるべきですが、そうすると南の借景が薄まるので、そこは欲張らずあえて存在感がうすい小さな窓にしています。
開放的な南面の窓を強調させたいのと、食事する際にさりげなく見えたらいいかなと。
ちょっとしたことなんですが、窓の存在で落ち着かなくなります。
この窓は開き戸で障子にすると障子を開かないと景色は見えないので、閉めたままでも程よく見える簾戸にしました。夏には涼しい印象もあります。