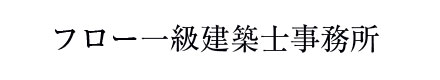「この写真の土間は何を使ってるんですか」と
問い合わせがあったのでご紹介を。
これは三和土(タタキ)といってセメントがなかった時代に使われていた代表的な土間のひとつです。
なぜ「三和土」と書いてタタキかというと、土、石灰、にがり3つの素材を混ぜわせて締め固めて何度も叩く(たたく)ことからきたらしいです。
「ほたるの家」の玄関のタタキの施工様子を少し撮ってみました。
ほんとに叩いて仕上げています。(笑)
腕パンパンになるみたいです。(笑)
「身近にある土を使って叩いて仕上げる」昔の人が考えた理にかなった工法です。
コンクリートやアスファルトの土間はとても簡単に施工できるもので、今ではとても主流になっていますが、夏場のコンクリートは触ると火傷をしてしまうぐらい、熱く、その照り返しからくる熱で周囲を暑くなっています。
三和土の土は必要以上に熱を吸収しないので、コンクリートで造った土間と比べると、確実に涼しいです。
以前に日本最古の民家住宅と呼ばれている兵庫の重要文化財「箱木千年家」を見学にいったのですが、三和土が使われていました。
真夏の時期だったのですが、家の土壁も含めて地面から熱気は感じることのなく、むしろひんやりとした空気を感じることができました。


夏の日射熱をどう遮断させるかによって夏の快適性はずいぶん変わってきます。
建物の断熱に着眼しがちですが、このように土を利用して日射熱を緩和させたり、畜冷、蓄熱させることで温熱環境はずいぶんよくなり省エネになります。
三和土の長所を紹介しましたが、短所もあります。
セメントで固めた土間と比べると、柔らかいので、雑にごしごしと洗うと土が欠けることもあります。
欠けても90mmくらいの厚みの土でできていますので、問題ないです。
あとは、左官の土間なの表面に小さなひび割れは出てきます。
これはコンクリートの土間も同じことです。
室内土間やアプローチにこの三和土を使うと庭との繋がりもあり自然を取り込んだような空間になるのでお勧めです。
なかなかできる左官屋さんや庭師さんが少なくなってきたので、もっと需要が上がるように勧めていきたいなと思っています。